世界は五反田から始まった(10) 疎開|星野博美

初出:2019年10月25日刊行『ゲンロンβ42』
父と私は、戸越銀座にある同じ品川区立の小学校の出身である。選挙があるたびにその小学校を訪れる。昨今はセキュリティが強化されて自由に出入りすることができないため、選挙は母校を訪れるまたとない機会でもある。
校門から中に入ると、かつて私も耕したことのある小さな水田がある。その水田の前には銅像が立っている。二宮金次郎ではなく、愛らしい女児の銅像だ。防災頭巾をかぶり、布製の鞄を斜めがけにして、もんぺを履いた女の子である。ぷくぷくと太り、満面の笑みを浮かべて、実にかわいらしい。ほとんどの人はその存在にすら気づかず素通りしていくが、私は必ずこの銅像に軽く会釈をすることにしている。像の足元に貼りつけられた銅板のプレートはすでに風化が始まり、かなり読みづらくなっているが、こう書かれている。
この銅像は卒業生からの寄付金で作られ、平成11(1999)年3月に完成した。そしてその年の卒業式、6年生とともに、「1944年の6年生」が一緒に卒業式を行った。彼らが卒業するはずだったのは、1945年3月。周知の通り、東京大空襲があった月だ。
その老いた卒業生の中に、当時66歳だった父がいた。「お向かいのMさんの孫と一緒に卒業したんだよ」と、思い出しては照れ笑いをする。
戦争の激化に伴い、都市防衛の強化と学童身命の防護を目的に、政府が学童集団疎開を閣議決定したのは昭和19(1944)年6月30日のことだった。品川地域では、第一陣として8月4日に城南第二国民学校が西多摩郡瑞穂町へ出発。続いて諸学校が八王子市、西・南多摩郡、静岡県、富山県へと学童たちを送り出した。静岡に疎開した児童たちの一部は、静岡が米軍の攻撃対象に含まれているという理由から、さらに青森へ疎開。八王子に疎開した児童の中には、終戦間際の八王子空襲によって命を落とした子どももいた。
校門から中に入ると、かつて私も耕したことのある小さな水田がある。その水田の前には銅像が立っている。二宮金次郎ではなく、愛らしい女児の銅像だ。防災頭巾をかぶり、布製の鞄を斜めがけにして、もんぺを履いた女の子である。ぷくぷくと太り、満面の笑みを浮かべて、実にかわいらしい。ほとんどの人はその存在にすら気づかず素通りしていくが、私は必ずこの銅像に軽く会釈をすることにしている。像の足元に貼りつけられた銅板のプレートはすでに風化が始まり、かなり読みづらくなっているが、こう書かれている。
「私たちが小学生のとき戦争がありました。戦争は相手の国の人々との殺し合いです。
空襲で家を失い、懐かしい校舎も焼かれ、大好きな先生も戦死され、友達もたくさん失いました。学童疎開では、毎日家へ帰りたくて泣いてばかりいました。
私たちが経験したこの恐ろしい戦争が、再びあなた方の前に起きてはならないし、起こしてはいけないのです。
何よりも生命を尊び、平和を大切にしていかなければなりません。
一九四四年に六年生だった卒業生より」
この銅像は卒業生からの寄付金で作られ、平成11(1999)年3月に完成した。そしてその年の卒業式、6年生とともに、「1944年の6年生」が一緒に卒業式を行った。彼らが卒業するはずだったのは、1945年3月。周知の通り、東京大空襲があった月だ。
その老いた卒業生の中に、当時66歳だった父がいた。「お向かいのMさんの孫と一緒に卒業したんだよ」と、思い出しては照れ笑いをする。
戦争の激化に伴い、都市防衛の強化と学童身命の防護を目的に、政府が学童集団疎開を閣議決定したのは昭和19(1944)年6月30日のことだった。品川地域では、第一陣として8月4日に城南第二国民学校が西多摩郡瑞穂町へ出発。続いて諸学校が八王子市、西・南多摩郡、静岡県、富山県へと学童たちを送り出した。静岡に疎開した児童たちの一部は、静岡が米軍の攻撃対象に含まれているという理由から、さらに青森へ疎開。八王子に疎開した児童の中には、終戦間際の八王子空襲によって命を落とした子どももいた。
現在の品川区を形成する品川・荏原地区別で疎開先を見ると、品川地区の疎開先が東京三多摩地区、荏原地区は静岡(のちに青森)と富山だった。父が学童疎開をしていたなら、静岡か富山になっていたはずだ。東京都から集団疎開した学童は23万7千人といわれる。
しかし父は幸運にも(と言ってよいだろう)、学童疎開をせずに済んだ。戦争の激化を懸念した祖父が、もう1軒家を買い、家族を独自に疎開させたからだ。学童疎開させない方針は、実は祖母の意向が強かった、と父は言う。ふだん自己主張などほとんどしない祖母が、子どもを手放すことについては断固拒否したのだそうだ。
軍需部品を作る祖父は、仕事が忙しくなればなるほど、軍からの突貫工事の依頼が増えれば増えるほど、戦争の激化を肌で感じられる立場にあった。黙々と軍の下請けをこなしながら、戦火を避ける算段をひそかに考え始めていたのだ。
「山国」「山辺」というざっくりした書き方が、外房の漁師の息子だった祖父らしい。米軍機は海のほうからやってくる。山のほうがより安全だ、という感覚があったのだろう。
祖父が言う「玉川の家」だが、私が祖父から実際に聞かされたのは「大森の家」だった。しかし父に確認すると、「雪ヶ谷だ」と言う。大森なのか、雪ヶ谷なのか……。調べてみたら、なんということはなく、当時の住所表記が「東京都大森区雪ヶ谷町」だっただけのことだ。この家に父は一度も行ったことはないが、こちらは比較的早くから手に入れていたらしい。
しかし父は幸運にも(と言ってよいだろう)、学童疎開をせずに済んだ。戦争の激化を懸念した祖父が、もう1軒家を買い、家族を独自に疎開させたからだ。学童疎開させない方針は、実は祖母の意向が強かった、と父は言う。ふだん自己主張などほとんどしない祖母が、子どもを手放すことについては断固拒否したのだそうだ。
軍需部品を作る祖父は、仕事が忙しくなればなるほど、軍からの突貫工事の依頼が増えれば増えるほど、戦争の激化を肌で感じられる立場にあった。黙々と軍の下請けをこなしながら、戦火を避ける算段をひそかに考え始めていたのだ。
これからも時々空襲もあるのではないか。田舎の親せき等へソカイする人も出て来た。又小学校の生徒も集団で山国のお寺とかお宮へソカイする学校もあった。
私も玉川に近い町に二十五坪(当時二万円)の家を買ってあった。が玉川でも戸越でも空襲は殆ど同じ、も少し遠い山辺の方へソカイすべく毎朝の様に新聞を見ては出かけてみたが適当な所はなかった。
「山国」「山辺」というざっくりした書き方が、外房の漁師の息子だった祖父らしい。米軍機は海のほうからやってくる。山のほうがより安全だ、という感覚があったのだろう。
祖父が言う「玉川の家」だが、私が祖父から実際に聞かされたのは「大森の家」だった。しかし父に確認すると、「雪ヶ谷だ」と言う。大森なのか、雪ヶ谷なのか……。調べてみたら、なんということはなく、当時の住所表記が「東京都大森区雪ヶ谷町」だっただけのことだ。この家に父は一度も行ったことはないが、こちらは比較的早くから手に入れていたらしい。
いま広く読んでほしい、東京の片隅から見た戦争と戦後
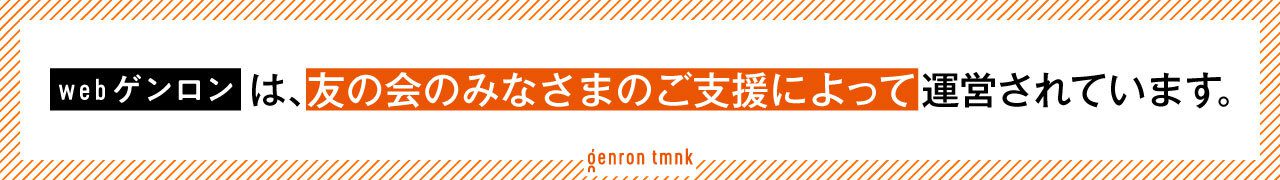

星野博美
1966年東京・戸越銀座生まれ。ノンフィクション作家、写真家。『転がる香港に苔は生えない』(文春文庫)で第32回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『コンニャク屋漂流記』(文春文庫)で第2回いける本大賞、第63回読売文学賞「紀行・随筆」賞受賞。主な著書に『戸越銀座でつかまえて』(朝日文庫)、『島へ免許を取りに行く』(集英社文庫)、『愚か者、中国をゆく』(光文社新書)、『のりたまと煙突』(文春文庫)、『みんな彗星を見ていた―私的キリシタン探訪記』(文春文庫)、『今日はヒョウ柄を着る日』(岩波書店)など、写真集に『華南体感』(情報センター出版局)、『ホンコンフラワー』(平凡社)など。『ゲンロンβ』のほかに、読売新聞火曜日夕刊、AERA書評欄、集英社学芸WEBなどで連載中。
世界は五反田から始まった
- 第2章 軍需工場──『世界は五反田から始まった』より|星野博美
- 第1章 大五反田──『世界は五反田から始まった』より|星野博美
- 世界は五反田から始まった(最終回) 星野製作所の最期|星野博美
- 世界は五反田から始まった(28) 焼け野原(5)|星野博美
- 世界は五反田から始まった(27) 焼け野原(4)|星野博美
- 世界は五反田から始まった(26) 焼け野原(3)|星野博美
- 世界は五反田から始まった(25) 焼け野原(2)|星野博美
- 世界は五反田から始まった(24) 焼け野原(1)|星野博美
- 世界は五反田から始まった(23)「回避」|星野博美
- 世界は五反田から始まった(22) 武蔵小山の悲哀(4)|星野博美
- 世界は五反田から始まった(21) 武蔵小山の悲哀(3)|星野博美
- 世界は五反田から始まった(20) 武蔵小山の悲哀(2)|星野博美
- 世界は五反田から始まった(19) 武蔵小山の悲哀|星野博美
- 世界は五反田から始まった(18) エッセンシャルワーカー|星野博美
- 世界は五反田から始まった(17) 赤い星|星野博美
- 世界は五反田から始まった(16)アイウエオの歌|星野博美
- 世界は五反田から始まった(15) スペイン風邪|星野博美
- 世界は五反田から始まった(14) 荏原無産者託児所|星野博美
- 世界は五反田から始まった(13) 党生活者2|星野博美
- 世界は五反田から始まった(12) 党生活者|星野博美
- 世界は五反田から始まった(11) ゆみちゃんとパラシュート|星野博美
- 世界は五反田から始まった(10) 疎開|星野博美
- 世界は五反田から始まった(09) 乳母日傘|星野博美
- 世界は五反田から始まった(08) 軍需工場|星野博美
- 世界は五反田から始まった(07) 「池田家だけが残った」|星野博美
- 世界は五反田から始まった(06) 「戻りて、ただちに杭を打て」|星野博美
- 世界は五反田から始まった(05) 焼けて、野原|星野博美
- 世界は五反田から始まった(04) 「Phantom of Gotanda」|星野博美
- 世界は五反田から始まった(03)「大五反田主義」|星野博美
- 世界は五反田から始まった(02)「逓信病院」|星野博美
- 世界は五反田から始まった(01)「Since 1916」|星野博美





