イスラームななめ読み(1) イスラミック・ポップとヨーロッパ |松山洋平

初出:2019年9月26日刊行『ゲンロン10』
「ヨーロッパがわれらの故郷。イスラームがわれらの信仰」。
これは、90年代にヨーロッパ・イスラーム諸機構連合(The Federation of Islamic Organizations in Europe)の会長アハマド・ラーウィー(أحمد كاظم فتحي الراوي:1947年生)が発したメッセージである[★1]。
20世紀後半、ヨーロッパに住むムスリムの数は大幅に増加した。ヨーロッパしか知らない「二世」「三世」の割合も増えていき、20世紀終盤には、多くのムスリムが、エスニック上の起源を持つ「祖国」ではなく、自分たちが居住するヨーロッパの国を自分の「故郷」と捉えるようになった。ラーウィーの言葉は、20世紀末に生まれたこうした新しいムスリム・アイデンティティの形を端的に言い表している。
今日、パリやロンドンをはじめ、ヨーロッパのいくつかの主要都市では、ムスリムは住民の一部として溶け込んでいる。ヨーロッパの一国に生まれ、その国の言葉を母語とし、その国の国民として人生を送るムスリムは増え続けてきた。
排外主義者の間では、ムスリムによるヨーロッパの「のっとり」を警戒する声もある。ムスリムは、ヨーロッパで子孫を増やしヨーロッパをのっとろうとしている、という主張である。たしかに、ヨーロッパのムスリム人口は、日本の一般的な想像をはるかに超えるペースで増加している。2050年には、ムスリムの数はフランスやドイツで人口の2割程度に達し、スウェーデンでは人口の3割を超える可能性もある[★2]。「のっとる」とまではならないとしても、ヨーロッパの「イスラーム化」は緩やかに進んでいる。排外主義者の懸念は、無根拠の妄想というわけでもない。
フランスが「イスラーム国家」と化す近未来を描いたミシェル・ウエルベック(Michel Houellebecq)の『服従』(Soumission)は日本でも話題を呼んだが、この小説は、現実離れしたファンタジーを描いたものではなく、ヨーロッパが今後辿ることになる一つの可能なシナリオを描いた作品として読むこともできる。
ヨーロッパに根付くムスリムの間には、新しい文化や宗教実践も生まれている。イスラーム宗教歌とポップカルチャーの融合はその一つである。
これは、90年代にヨーロッパ・イスラーム諸機構連合(The Federation of Islamic Organizations in Europe)の会長アハマド・ラーウィー(أحمد كاظم فتحي الراوي:1947年生)が発したメッセージである[★1]。
20世紀後半、ヨーロッパに住むムスリムの数は大幅に増加した。ヨーロッパしか知らない「二世」「三世」の割合も増えていき、20世紀終盤には、多くのムスリムが、エスニック上の起源を持つ「祖国」ではなく、自分たちが居住するヨーロッパの国を自分の「故郷」と捉えるようになった。ラーウィーの言葉は、20世紀末に生まれたこうした新しいムスリム・アイデンティティの形を端的に言い表している。
今日、パリやロンドンをはじめ、ヨーロッパのいくつかの主要都市では、ムスリムは住民の一部として溶け込んでいる。ヨーロッパの一国に生まれ、その国の言葉を母語とし、その国の国民として人生を送るムスリムは増え続けてきた。
排外主義者の間では、ムスリムによるヨーロッパの「のっとり」を警戒する声もある。ムスリムは、ヨーロッパで子孫を増やしヨーロッパをのっとろうとしている、という主張である。たしかに、ヨーロッパのムスリム人口は、日本の一般的な想像をはるかに超えるペースで増加している。2050年には、ムスリムの数はフランスやドイツで人口の2割程度に達し、スウェーデンでは人口の3割を超える可能性もある[★2]。「のっとる」とまではならないとしても、ヨーロッパの「イスラーム化」は緩やかに進んでいる。排外主義者の懸念は、無根拠の妄想というわけでもない。
フランスが「イスラーム国家」と化す近未来を描いたミシェル・ウエルベック(Michel Houellebecq)の『服従』(Soumission)は日本でも話題を呼んだが、この小説は、現実離れしたファンタジーを描いたものではなく、ヨーロッパが今後辿ることになる一つの可能なシナリオを描いた作品として読むこともできる。
ヨーロッパに根付くムスリムの間には、新しい文化や宗教実践も生まれている。イスラーム宗教歌とポップカルチャーの融合はその一つである。
2000年代から、ピアノやギター、ドラムセット、シンセサイザーなどを用いた現代洋楽風の曲に、イスラームの伝統的な価値や教えを表現する英語の歌詞や、象徴的なMVを合わせる音楽が盛んに発信されるようになった。こうした音楽の発信は、ヨーロッパのムスリムがヨーロッパ人としてのアイデンティティを獲得する現象と並行して拡大した。
本稿では、この種の音楽を「イスラミック・ポップ」ととりあえず呼んでおきたい。
イスラミック・ポップは、欧米に居住するムスリムのみならず、イスラーム諸国のムスリムの間でも多くのファンを獲得することに成功した。ヨーロッパを主要な発信源とする、21世紀に確立したイスラームにおける新しい宗教音楽のジャンルと言える──あるいは、イスラームの新しい宗教文化と言ってもよいかもしれない[★3]。
さきがけとなったのは、サーミー・ユースフ(Sami Yusuf:1980年生)というイギリス人の歌い手である。2003年のデビュー後間もなくして、彼の洋楽風のイスラーム宗教歌は、欧米から中東、東南アジアまで、世界各地のムスリムの間に浸透した。一部のアラブ諸国では、街角でも彼の音楽が流れた[★4]。デビュー・アルバムの『Al-Mu’allim』はミリオンセラーとなり、2019年現在、これまでリリースされた彼の8枚のスタジオ・アルバムは総計3400万枚の売上を記録している[★5]。
2009年にデビューしたスウェーデン人のマーヒル・ゼイン(Maher Zain:1981年生)は、サーミー・ユースフと並ぶイスラミック・ポップ界二大巨頭の一人である。サーミー・ユースフよりも大衆性の強い楽曲で人気を博している。アメリカ人のラーエフ(Raef:1982年生)のように、Michael JacksonやMaroon 5、Chris Brownなどの楽曲の「イスラミック・カバー」を発信する斬新な試みを行っている歌い手もいる。
マーヒル・ゼイン、ラーエフらをプロデュースしているのは、ロンドンのアウェイクニング・レコード社(Awakening Records)である。2000年に立ち上げられた同社は、2003年にサーミー・ユースフと契約を結んで以来、この分野を牽引する存在となった(サーミーとは2009年に契約を終了している)。イスラミック・ポップがサーミー・ユースフという才能ある一個人の活動で完結せず、一つの大きな分野として確立したのは、同社の功績によるところも小さくない。
2013年、アウェイクニング・レコード社は、新人発掘のための世界規模のコンテストを開催した。このコンテストを勝ち抜き、イスラミック・ポップ界の新たなスターとして世界に名を知らしめたのは、16歳のイギリス人、ハリス・J(Harris J:1997年生)であった。サーミー・ユースフやマーヒル・ゼインから見ると一世代若い、「新世代」の歌い手と言える。
本稿では、この種の音楽を「イスラミック・ポップ」ととりあえず呼んでおきたい。
イスラミック・ポップは、欧米に居住するムスリムのみならず、イスラーム諸国のムスリムの間でも多くのファンを獲得することに成功した。ヨーロッパを主要な発信源とする、21世紀に確立したイスラームにおける新しい宗教音楽のジャンルと言える──あるいは、イスラームの新しい宗教文化と言ってもよいかもしれない[★3]。
さきがけとなったのは、サーミー・ユースフ(Sami Yusuf:1980年生)というイギリス人の歌い手である。2003年のデビュー後間もなくして、彼の洋楽風のイスラーム宗教歌は、欧米から中東、東南アジアまで、世界各地のムスリムの間に浸透した。一部のアラブ諸国では、街角でも彼の音楽が流れた[★4]。デビュー・アルバムの『Al-Mu’allim』はミリオンセラーとなり、2019年現在、これまでリリースされた彼の8枚のスタジオ・アルバムは総計3400万枚の売上を記録している[★5]。
2009年にデビューしたスウェーデン人のマーヒル・ゼイン(Maher Zain:1981年生)は、サーミー・ユースフと並ぶイスラミック・ポップ界二大巨頭の一人である。サーミー・ユースフよりも大衆性の強い楽曲で人気を博している。アメリカ人のラーエフ(Raef:1982年生)のように、Michael JacksonやMaroon 5、Chris Brownなどの楽曲の「イスラミック・カバー」を発信する斬新な試みを行っている歌い手もいる。
マーヒル・ゼイン、ラーエフらをプロデュースしているのは、ロンドンのアウェイクニング・レコード社(Awakening Records)である。2000年に立ち上げられた同社は、2003年にサーミー・ユースフと契約を結んで以来、この分野を牽引する存在となった(サーミーとは2009年に契約を終了している)。イスラミック・ポップがサーミー・ユースフという才能ある一個人の活動で完結せず、一つの大きな分野として確立したのは、同社の功績によるところも小さくない。
2013年、アウェイクニング・レコード社は、新人発掘のための世界規模のコンテストを開催した。このコンテストを勝ち抜き、イスラミック・ポップ界の新たなスターとして世界に名を知らしめたのは、16歳のイギリス人、ハリス・J(Harris J:1997年生)であった。サーミー・ユースフやマーヒル・ゼインから見ると一世代若い、「新世代」の歌い手と言える。
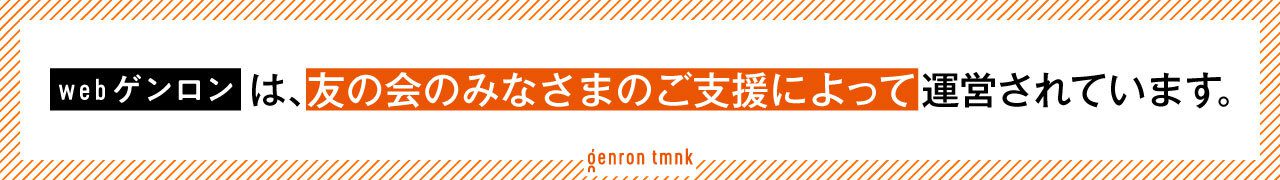

松山洋平
1984年静岡県生まれ。名古屋外国語大学世界教養学部准教授。専門はイスラーム教思想史、イスラーム教神学。東京外国語大学外国語学部(アラビア語専攻)卒業、同大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了。博士(学術)。著書に『イスラーム神学』(作品社)、『イスラーム思想を読みとく』(ちくま新書)など、編著に『クルアーン入門』(作品社)がある。
イスラームななめ読み
- 『ゲンロン14』特設ページ
- イスラームななめ読み(10) これからのクルアーン翻訳、あるいはアダプテーション|松山洋平
- イスラーム教と現代日本の宗教観
- イスラームななめ読み(8) ニッポンのムスリムが自爆するとき|松山洋平
- イスラームななめ読み(7) 田舎者のサイバー・ジハード|松山洋平
- イスラームななめ読み(6) 日本・イスラーム・文学──中田考『俺の妹がカリフなわけがない!』について|松山洋平
- ノックの作法と秘する文化
- イスラームななめ読み(4) アッラーのほか、仏なし|松山洋平
- イスラームななめ読み(3) 大日本帝国の汎イスラム主義者|松山洋平
- イスラームななめ読み(2)「イスラム」VS.「イスラム教」|松山洋平
- イスラームななめ読み(1) イスラミック・ポップとヨーロッパ |松山洋平



